
香港での資産運用は貯蓄型生命保険がおすすめ!日本との違いを解説
香港に長期間住んでいる、駐在している方におすすめなのが、香港での資産運用です。おすすめする理由としては、日本での資産運用ができなくなったことがあります。また、香港にいる利点を活かしたうえで資産運用ができるからです。 本記事では、香港の貯蓄型生命保険の特徴や日本の貯蓄型生命保険との違い、海外移住者の資産運用として優れている理由について解説します。香港在住の利点を活かし、資産運用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。 \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら 1.香港の貯蓄型生命保険とは 香港の貯蓄型生命保険は、保障機能と貯蓄機能および資産運用機能を併せ持った保険です。日本の貯蓄型生命保険と同様に、払い込んだ保険料が保険会社によって運用され、運用状況に応じて配当金が支払われます。また、途中で解約した場合には解約返戻金を受け取ることができます。万が一、契約期間中に被保険者が死亡した場合は死亡保険金が支払われる点は、日本の生命保険と同じです。 1-1.日本の貯蓄型保険と異なる点 香港の貯蓄型生命保険には、日本のものとはまったく異なる特徴もあります。 契約期間が長い 被保険者の変更(契約承継)ができる 証券分割ができる 商品によっては契約期間中に運用通貨を変更できる 保険料の一時払込み休止オプションなど自由度が高い 商品によっては奨学金をもらえるものもある 2.海外移住者の資産運用に優れている理由 一般的に、資産運用の方法には株式、投資信託、不動産などもあります。これまで日本で資産運用をされた経験のある方は、香港でもこれらの方法で資産運用をしようと検討している方もいるかもしれません。 香港に移住された方、または長期間駐在の予定がある方には、香港での資産運用には貯蓄型生命保険がおすすめです。その理由を解説していきます。 2-1.高い利回りを期待できる 香港の貯蓄型生命保険は日本の貯蓄型保険よりも高利回りのものが多く、高いリターンを期待できます。香港は、世界のなかでも主要な国際金融センターとして高い運用ノウハウを持つ大手金融機関が世界中から集まっているためです。 香港では、資産運用への高いノウハウを持った保険会社が、独自の運用方針のもと、株式や債券などに分散投資をしています。個人で株式個別銘柄に分散投資をする場合、多額の元手が必要となるうえ、銘柄選択やポートフォリオの入れ替えタイミングを測るのも大変です。1つの保険商品で分散投資を行える、且つ安定的に高いリターンを得られるメリットは大きいでしょう。 運用で得られる配当金を年金のように毎年少しずつ引き出して使いながら、そのまま運用を続けていくことで資産の枯渇を防ぐこともできるでしょう。 2-2.複数の通貨で資産を分散できる 将来のインフレ等に備えて日本円以外の資産を持っておくのは、資産運用におけるリスク管理のひとつです。その点、香港の貯蓄型生命保険はいわゆる「外貨」で運用をするため、リスク管理として有効です。 選べる通貨の種類数は異なるものの、ひとつの保険で運用通貨を切り替えたり、証券分割して複数の通貨に分けたりできる商品もあります。海外移住者は将来的に自分自身や家族が別の国へ移住することも多いため、さまざまな通貨で運用しておくことで将来的な外貨資産ニーズに対応できるでしょう。 2-3.証券分割ができる 海外生活経験がある人ほど、ご家族の各人も留学やビジネスでグローバルに活動する傾向があります。初めて記事を目にする人にはイメージが湧きにくいかもしれませんが、香港の貯蓄型生命保険は証券分割して複数の契約に分けられるので、資産を分け与えてそれぞれの資金需要に対応することもできます。 つまり、銀行にあるお金を分け与えるようなイメージではありつつ、運用は継続されたまま、さらに保険の権利も含め分割譲渡できます。日本では非常識ですが香港ならではの常識です。日本人にとっても得られるメリットは多いでしょう。 2-4.相続手続きが容易である 香港の貯蓄型生命保険は、あくまでも生命保険です。一般的な生命保険と同様に、自分に万一のことがある場合のためにあらかじめ保険金の受取人を決めておくことができます。それにより、遺産分割のトラブルを避けられるほか、保険金は受取人の固有資産となるメリットがあります。 後者のメリットは、海外移住者にはとても大切なポイントです。相続が発生した時(死亡時)にご自身や相続人がどこに住んでいるかにもよりますが、日本人が日本国外にある預金口座や証券口座、不動産などを相続する場合、国際相続となります。国際相続は手続きが煩雑であるため高いノウハウのある弁護士への依頼が必要になり、一般的に高額な報酬の支払いが必要になります。加えて弁護士に依頼したとしても、相続人が資産を受け取れるまでには長い期間がかかります。そのため海外移住者が海外で資産運用をする場合には、保険という形で資産を保有しておくのがとても有用ではないかと考えています。香港では貯蓄型生命保険が効果的です。 3.実際、どの程度のリターンを期待できる? 将来的に期待できるリターンは保険会社や保険商品のほか、保険料払込期間、経過期間(解約時期)などのさまざまな条件で変わります。また、運用する通貨によって投資対象が異なりますので、同じ保険商品でも運用通貨が変わればリターンも変動します。 総合的には、契約してから5〜6年程度で損益分岐点を迎え、10年で120〜150%、20年で240〜300%、30年で500〜600%程度と高いリターンを期待できるものが多いようです。実際にシミュレーションを見てみたい方は、ぜひ110(ワンテン)へお問い合わせください。 なお、実際に加入を検討される際は、期待リターンの数字だけではなく、資産運用の目的や資金が必要な時期に合わせて適した商品を選ぶことが大切です。自分が老後に使いたい、子どもの海外留学資金や事業資金を準備したい、家族に資産を承継したいなど、目的は違っても対応できる貯蓄型生命保険が見つかるはずです。 香港の貯蓄型生命保険でリスクに強い資産運用を 資産運用としての機能と保険としての機能を併せ持つ香港の貯蓄型生命保険は、香港に在住している人の資産運用方法としておすすめです。日本の貯蓄型生命保険や、株式、投資信託、不動産などの資産運用とは異なるメリットが多々あります。商品の種類も豊富で、海外在住者の幅広いニーズに対応できます。駐在をはじめ香港に移住されている方は、ご自身やご家族のためにぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。 海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ 1998年に香港で金融サポートを開始したNNI香港の個人保険部門である「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規の保険BROKERとしての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、日本でのFP経験もあり日本事情にも精通する経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。 海外での資産運用が初めてで少し不安 今の資産運用状況についてのアドバイスが欲しい iDeCo/NISAや老後の年金について知りたい といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。 \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら

香港の学資保険を徹底解説!香港在住者・駐在員は必見!
子どもの教育資金は、将来の夢を実現するための必要不可欠な投資です。円安時も外貨で運用できる安心感があります。この記事では、香港で提供されている学資保険に焦点を当て、日本との違いやおすすめのプランを詳しく解説します。 香港の学資保険の特長は、その高い返戻率にあり、これにより教育資金の効果的な運用が可能です。各保険会社や金融機関が提供する商品には、それぞれ独自のメリットがあるため、ぴったりのプランを見つけ出しましょう。 さらに、この記事では、海外での進学を含む教育資金の計画方法や、高校や大学入学前に行うべき準備についても詳しく紹介します。香港の学資保険をうまく利用して、お子様の将来の夢を全力でサポートしましょう。 \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら 学資保険とは 学資保険とは、子どもの教育資金を準備する目的で利用される保険商品です。契約者が一定の期間、保険料を支払うことで、子どもが大学などの高等教育機関に進学するタイミングで教育資金が受け取れる仕組みです。 具体的には、契約時に選択した満期時点で一定の金額が受け取れるため、その資金を子どもの学費に充てることができます。 学資保険は日本だけでなく、香港でも人気のある保険商品で、香港の学資保険には独自の特徴があります。例えば、香港ドルや米ドルでの契約が可能であり、日本円への換算が必要な場合でも香港の金融機関を活用することでスムーズに帰国後の支払いができます。 自身で契約する保険会社や商品を選ぶ際には、香港の保険会社が提供する学資保険商品を比較検討することにより、最適なプランを見つけ出すことができます。ぜひ、お子さまの将来のために香港での学資保険準備のメリットについて検討してみてはいかがでしょうか? 香港における学資保険について解説 香港における学資保険は、子どもの将来の学資や生活費を効率的に貯蓄・運用することを目的とした保険商品です。以下では香港の学資保険の特徴や違いについて詳しく解説するため、ぜひ最後までお読みください。 香港ドルや米ドルでの契約が可能 高い返戻率 香港の学資保険は柔軟性が高く、契約期間や支払方法を選択できます。例えば、月々の支払いだけでなく、半年や一括での支払いも選べるため、自分の経済状況に合わせて選べるメリットがあります。また、香港の学資保険は、返戻率が高いことも特徴です。支払った保険料に対して返戻率が15〜20年後に2倍、30年後に5倍、40年後に10倍近くとなるものがあります。 香港の学資保険は日本とどう違う? 香港の学資保険は、日本の学資保険と比較すると、以下の違いがあります。 柔軟な運用が可能で、進学や将来のために資金を継続的に運用しやすい 保険の途中で一部を引き出すこともできるため、子どもの進学費用や老後の資金に活用できる これらの違いから、香港の学資保険は日本の学資保険に比べてより自由度が高く、資金の活用がしやすいです。香港の学資保険では、子どもが一定の年齢に達したあとは解約返戻金を年金として定期的に受け取ることができるオプションが付帯しています。さらに子どもが日本非居住者であれば、契約名義人として親から引き継いだり、被保険者を自身の子ども (親から見て”孫”)に変更することも可能です。 教育資金プランニング お子様の将来に備えて教育費を準備するために、プランニングが必要です。理想の教育環境を提供するため、確実な資金計画を立てましょう。ここからは、現代の教育費のリアルな状況をお伝えし、学資保険の積立や運用方法についても詳しく解説します。ぜひ、将来の教育資金計画に役立ててください。 現代の教育費のリアルな状況 現代の教育費は、伸びない収入の中でも年々高騰しており、両親にとっては大きな負担となっているのも事実です。 国公立、私立それぞれの学校により、教育費はさまざまですが、文部科学省の調査によると、平成30年の大学進学者1人あたりの授業料・入学料など合計金額は、国公立で約270万円、私立で約560万円です。これに加えて、学習塾や進学準備の費用も考慮する必要があります。 お子さまの将来に備えるため、両親はすべての費用を無理のない範囲で計画し、準備しておくことが大切です。子どもの誕生時から資金計画を立て、適切な保険商品を選ぶことで、より安心して教育資金を揃えることができます。 学資保険の積立や運用方法 学資保険には、さまざまな積立や運用方法があります。まず、保険会社が提供する学資保険に加入し、一定期間毎に保険料を支払うことで、子どもの進学時に必要な資金を確保できます。また、学資保険とはいえ、基本的には、運用商品です。、ただ現預金を置いておくだけではなく資産運用を行いながら資金を増やすことができます。 高校や大学までの期間が差し迫っている場合は、金融機関での定期預金やリスクを承知の上で投資信託の活用も、教育資金の準備方法の一つと言えるでしょう。。 ですが、早めに備えておくことが重要で、運用時間が長いと管理されたリスクの中で複利効果もあり十分に備えることができます。運用時間が短いと低金利の定期預金という選択肢や、大きいリターンを求めて投資信託を利用するなど、低リスクか高リスクな選択肢となり、十分な運用成果を得られない可能性もあります。 海外進学も計画的にサポート そこで、海外進学を計画的にサポートするためには、長期・複利運用を実現できる学資保険を活用することが現実的です。特に香港の学資保険は、米ドル建ての運用でありながら、変動リスクが低く運用リスクも比較的低いため、日本の学資保険と比較すると結果に雲泥の差がでます。さらに為替リスクに対しても、昨今の国外での教育費増加に対しても対応可能と考えられます。 万が一、死亡した時には保障が免除される特約もあり、運用中の大黒柱の万一リスクに対しても、備えることが可能です。香港の学資保険は、香港での留学や駐在員向けの特典やキャッシュバック・ボーナスが付与されるプランもあります。一定期間払い込みを続けることで、特典や増価を享受できるのも嬉しいですね! \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら おすすめの香港学資保険を紹介 これまでに紹介した海外進学のサポートを受けられる香港学資保険や、入学前の準備ポイントを参考に、おすすめの保険を選んで子どもの将来に備えましょう。 適切な商品選びや資金計画が子どもの教育や人生に大きな影響を与えます。ここではおすすめの香港学資保険を紹介します。 Vision(ビジョン) Visionは香港の保険で、利子の確定部分があります。これにより、運用しながら資産増大を目指せます。子どもや孫などに資産承継できるシステムがあるため、自分だけでなく家族のために資産運用したい人にもおすすめです。万が一に備える保険であまり運用に大きなリスクを背負いたくない場合でも、Visionであれば一部分は元本確保があるため、安心感が得られるでしょう。 詳細はこちら: 【サンライフ保険紹介】Vision(ビジョン)|米ドル建て貯蓄型保険 Commitment(コミットメント) Commitmentは、AIA香港が提供する終身保険プランで、以下の特徴があります。 自由な契約期間 安定したリターン 万が一の事態に備えた保障 Commitmentは最短で10年満期の運用も可能なため、資金需要を見越して比較的短い期間で資産を増やしたい人にも向いています。またCommitmentは、保証された現金価値と非保証の年次配当、非保証の終期配当を提供します。そのため安定したリターンが期待できるでしょう。保険料支払い期間中に契約者に万が一の事があった場合は、サンライフ社が保険料を負担し満期までプランが継続されます点も特徴です。万が一の事があっても、満期まで契約が継続されるため、計画通りの資金が受け取れます。 詳細はこちら: 【サンライフ保険紹介】Commitment(コミットメント)|米ドル建て貯蓄型保険 Simply Love Encore 5…

シンガポールの保険購入ステップ
シンガポールの保険購入ステップ シンガポールにて保険を購入する際に必要な書類・手続き等をまとめて解説! シンガポールでの生命保険加入を考えているけれども、具体的な書類や手続きはどんなものがあるのか気になる方のために、この記事では、各保険会社の保険購入のステップを詳しく説明していきたいと思います。 目次 ①申込から契約までのステップ➁各保険会社の必要書類及び手続き ③よくあるご質問 ④購入後の状況確認方法 ⑥まとめ 申込から契約までのステップ 申し込みが完了してから、契約が完了する(ここでは契約書類がお客様の手元に来るまで)までに、大きく分けて5つの段階があります。以下で、順番に説明していきます。 ①サイン済み申込書及び必要書類を保険会社に提出どの保険会社にも専用の申込書が用意されています。その申込の指示に従って、必要書類を準備します。保険販売代理店を通して契約をする場合は、その保険代理店から保険会社に提出されます。 ②保険会社による審査保険会社は申込書及び必要書類を受け取り後、いわゆるDue Diligenceを行い、顧客調査を行います。審査には1~2週間かかります。 ③審査終了後、支払い待ちの状態に保険会社の審査が終了すると、終了の通知が届き、契約自体はお客様の最初の保険料払い込み待ちの状態になります。通知の際に振込先等の情報も一緒に送付されます。 ④支払い完了を保険会社が確認後、契約書送付お客様による保険料の支払いが完了したのを保険会社が確認後、申込書に記載した住所宛てに契約書が送付されます。 ⑤契約書受け取り契約書を受け取ります。 以上が申し込みから契約書受け取り(契約完了)までの主な流れとなっています。 各保険会社の必要書類及び手続き ①Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd 【必要書類】a. パスポートのコピーb. 有効期間が6か月以上のビザのコピー(表裏)c. シンガポールの住所を証明するもの(シンガポール国内の住所宛ての光熱費の支払い領収書、賃貸借契約書等、直近6カ月の住所を証明するもの)d. 英訳の住民票除票e. シンガポール国内の銀行口座証明書 【支払方法】a. Tokio Marine Life Insurance Pte LtdまたはTMLSへ支払い可能な小切手b. クレジットカード(Master/Visa)c. HP(https://www.tokiomarine.com/sg)でAXSより支払う(“Life Insurance”を選択)。d. AXS機やAXSアプリe. インターネットバンキング:DBS Bill Payment(DBS及びPOSBインターネットバンキングご利用の方) ②Manulife Singapore Pte Ltd 【必要書類】a. パスポートのコピーb. ビザのコピー(表裏)c. シンガポール国内の住所を証明するもの(光熱費の領収書、賃貸借契約書等)d. 英訳の住民票除票e. シンガポールでの銀行口座※住民票除票の準備が難しい場合は以下で代用可能 【支払方法】a.…

円安?円高?海外保険、解約時のチェックポイント
情報化社会の現代では、投資に関する知識が簡単に手に入るようになりました。
しかし情報量が多すぎるために、何からはじめればよいのか分からない人も多いです。
そこでどのように資産運用をはじめていけばよいのか、初めての方にもわかりやすく説明しました。
今回は資産運用の考え方基礎編を3回にわたってお届けします。
第三回は「3つのカテゴリーでリスク分散」
さて、気になる3つカテゴリーとはどのようなものでしょうか?

外貨建て保険は不要
いずれは日本に帰国し日本の年金を受け取ることになる方が大半かと思います。特に若い世代の方ですと自分達の世代には破綻していてもらえないのでは?と心配する声もあります。ここで安心していただきたいのは年金が受け取れないということはありません。
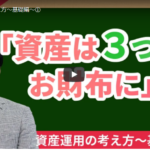
資産運用の考え方~基礎編~①
情報化社会の現代では、投資に関する知識が簡単に手に入るようになりました。
しかし情報量が多すぎるために、何からはじめればよいのか分からない人も多いです。
そこでどのように資産運用をはじめていけばよいのか、初めての方にもわかりやすく解説しました。
今回は資産運用の考え方基礎編を3回にわたってお届けします。
第一回は「資産は3つのお財布に」
さて、3つのお財布とはどのようなものでしょうか?
個人的見解にはなりますが、この動画が少しでも参考になれば幸いです。
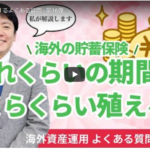
海外保険に関するよくある質問 – 第16弾
海外保険に関して、相談者からよくある質問にお答えしていきます。 今回は 「海外貯蓄保険を検討しているのですが、 どれくらいの期間でいくらくらい殖えるのでしょうか?」 というご質問をピックアップさせていただきました。 丁寧に解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。 安心で充実した海外ライフを送りましょう! ▼プロに無料で相談してみる ▼過去のよくある質問はこちらから ■海外保険に関するよくある質問 – 第1弾■海外保険に関するよくある質問 – 第2弾■海外保険に関するよくある質問 – 第3弾 ■海外保険に関するよくある質問 – 第4弾■海外保険に関するよくある質問 – 第5弾■海外保険に関するよくある質問 – 第6弾■海外保険に関するよくある質問 – 第7弾■海外保険に関するよくある質問 – 第8弾■海外保険に関するよくある質問 – 第9弾■海外保険に関するよくある質問 – 第10弾■海外保険に関するよくある質問 – 第11弾■海外保険に関するよくある質問 – 第12弾■海外保険に関するよくある質問 – 第13弾■海外保険に関するよくある質問 – 第14弾■海外保険に関するよくある質問 – 第15弾■海外保険に関するよくある質問 – 第16弾 ▼無料相談・セミナー開催中!
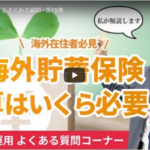
海外保険に関するよくある質問 – 第15弾
海外保険に関して、相談者からよくある質問にお答えしていきます。 今回は「海外貯蓄保険を検討しているのですが、 予算はいくらくらい必要ですか?」というご質問をピックアップさせていただきました。 丁寧に解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。安心で充実した海外ライフを送りましょう! ▼プロに無料で相談してみる ▼過去のよくある質問はこちらから ■海外保険に関するよくある質問 – 第1弾■海外保険に関するよくある質問 – 第2弾■海外保険に関するよくある質問 – 第3弾 ■海外保険に関するよくある質問 – 第4弾■海外保険に関するよくある質問 – 第5弾■海外保険に関するよくある質問 – 第6弾■海外保険に関するよくある質問 – 第7弾■海外保険に関するよくある質問 – 第8弾■海外保険に関するよくある質問 – 第9弾■海外保険に関するよくある質問 – 第10弾■海外保険に関するよくある質問 – 第11弾■海外保険に関するよくある質問 – 第12弾■海外保険に関するよくある質問 – 第13弾■海外保険に関するよくある質問 – 第14弾■海外保険に関するよくある質問 – 第15弾 ▼無料相談・セミナー開催中!
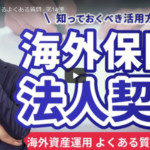
海外保険に関するよくある質問 – 第14弾
お客様から実際に相談をお受けした、海外保険に関する質問に回答します。 今回の質問は 「法人を契約者として香港保険に加入することはできますか? その場合の活用方法を教えてください。」 というものです。 海外保険のプロが詳しくお答えします。 ▼プロに無料で相談してみる ▼過去のよくある質問はこちらから ■海外保険に関するよくある質問 – 第1弾■海外保険に関するよくある質問 – 第2弾■海外保険に関するよくある質問 – 第3弾 ■海外保険に関するよくある質問 – 第4弾■海外保険に関するよくある質問 – 第5弾■海外保険に関するよくある質問 – 第6弾■海外保険に関するよくある質問 – 第7弾■海外保険に関するよくある質問 – 第8弾■海外保険に関するよくある質問 – 第9弾■海外保険に関するよくある質問 – 第10弾■海外保険に関するよくある質問 – 第11弾■海外保険に関するよくある質問 – 第12弾■海外保険に関するよくある質問 – 第13弾■海外保険に関するよくある質問 – 第14弾 ▼無料相談・セミナー開催中!

毎年安くなる熾烈な価格競争
実は日本の保険が激しい価格競争の結果、毎年安くなっていることをご存知でしょうか。
この20年で新しい保険会社がどんどん登場してきています。その背景には吸収合併で淘汰されている会社もありますが、新しい保険会社も続々登場しています。その結果益々保険料金の価格競争が激化しています。











