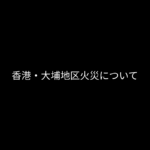長引く円安に加え、中国を含めた経済発展の影響により、香港と日本では生活費の面で最大2倍近くの差がでています。香港に長期間滞在する場合は、物価高騰を視野に入れた生活費のシミュレーションが必要です。この記事では、香港に長く滞在する方のために、日本との平均の生活費の比較と、香港で費用を抑えて暮らすためのかしこい節約術を解説します。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
1.香港での1か月の生活費を日本と比較

香港はここ数年、物価高の状態が続いており、日本と比較すると約1.5~2倍程度高い水準で推移しています。香港に滞在する場合は、現地の物価高を想定した生活費のシミュレーションが大切です。
ここでは香港での暮らしがイメージしやすいよう、都市部での滞在を前提として日本と香港の1か月の生活費を解説します。
1-1. 香港の生活費
香港での生活費で最も比率が高いのは家賃です。香港の家賃は、都市部の九龍周辺の場合、日本円にして安くても20万円前後です。ファミリータイプや、セキュリティーの高い部屋となると40万円から60万円と円安の影響もあり日本円換算での家賃はより高く感じます。
また、食材の物価高も続いているため、食費も高止まりの状態です。20代~30代の女性の1人暮らしでも、食費に約10万円がかかります。食費を抑えるためには、外食ではなく自炊をメインにすることで節約ができます。
水光熱費や交通費、娯楽費についても東京より高い水準が続いています。交通費を抑えるために、移動時はできる限りタクシーを使わずに自転車や徒歩にすることで節約につながります。また娯楽費は、1ヶ月に使用できる金額を決めることで費用を抑えられるでしょう。
1-2. 日本の生活費
反対に、東京都内で1人暮らしをする場合、1か月の生活費は平均で約15万円です。おおまかな内訳は以下の通りです。
- 家賃:88,000円
- 水道光熱費:9,732円
- 通信費:6,773円
- 食費:40,299円
- 家具・家事用品費:5,617円
もちろん、東京での1人暮らしも香港と同様、食費や光熱費、遊興費などの変動費を抑えることで節約ができます。
1-3. 家賃の相場が高い
日本と香港の生活費を比較した場合、大きな差が出るのは家賃です。単身世帯の場合、東京都内ではおおむね10万円以内で収まる一方、香港では同水準の物件で15万円を超えるケースも珍しくありません。
香港では長らく家賃相場の高騰が進んでおり、特に大都市圏では高止まりの状態が続いています。
駐在員として会社に家賃負担してもらう環境にするか、単身香港で働く場合は家賃相場に見合う仕事を見つける、もしくは比較的家賃の低い地方近郊で住まいを見つけるのがよいでしょう。
2.日本との物価の違い

近年、日本でもモノが高くなるインフレーションを肌で感じるようになってきましたが、香港の生活費高騰も、主に物価高(インフレーション)が要因です。
ここでは、日本と香港の物価の違いと、その内訳について見ていきましょう。
2-1.香港の物価は日本の約2倍
香港の物価は現時点で、日本の約2倍です。
消費者物価指数(CPI)で見た場合、2008年の71ポイントを境に右肩上がりが続いており、2024年現在で107ポイントに達しています。
特に香港では外食が一般的であり、その食費(外食費用)の上昇率が大きいことから、香港では生活費の高騰が問題視されているのが現状です。
2-2.香港には消費税がない
香港では日本と違い、消費税がありません。そのため、単純に商品価格のみで比較すると日本よりも安く感じる場合があります。
しかしながら、家賃などの上昇幅が大きいため、トータルの生活費で見ると日本よりも1.5倍~2倍になってしまうのが現状です。
また細かい部分では健康保険がないため病院へ支払う医療費が高い(盲腸や結石などで日本円で150万円ほど…)、また教育費も選択肢によっては、子供1人20万円前後かかるなど、日本の社会的インフラの良さとついつい比較してしまいます。
ただ、香港では過去にチップ文化が根づいていたこともあり、レストランやホテルなどのサービスでは代金の10%前後が消費税のようにサービスチャージとして上乗せされます。
いずれにせよ、お金があるとサービスや、生活もとても充実した環境であると言えますが、ギリギリの生活感だと大変ですね。
3. 香港の生活費が日本よりも高く感じる理由

ここでは、香港の生活費が日本よりも高騰していると感じる理由を見ていきましょう。
3-1.円安ドル高
2023年から24年にかけて、記録的な円安が続いています。
長引く円安にともなう世界的なドル高によって、米ドルとペッグしている香港ドルも高騰し、金利も高く香港の生活費高騰を誘引してしまう事が主な原因です。
円安が進行している状況では、まったく同じ商品・サービスを購入する場合でも通常よりも多くのお金が必要になります。
円安の影響は香港に限らず、日本人の海外滞在という面では大きなハードルとなっているのが現状です。逆に香港の人はその円安ドル高を活かして、香港での生活費をしっかりと節約して、安く感じる日本で買い物や、食事など充実した海外旅行をしているのが現状です。
パスポート保有率が15%程度の日本人には、日常的に国を跨ぐ生活というのはイメージしにくいかもしれません。
3-2.経済発展
香港の生活費高騰の背景には、経済発展があります。
2000年代以降、中国はめざましい経済発展を続けており、香港もその影響を受ける形で物価上昇が継続しています。
香港では2020年、「大湾区(GBA)」と呼ばれる巨大な行政・経済特区が誕生しました。大湾区は2つの経済特区を含み、観光・金融業を中心としてよりいっそうの発展を遂げています。
この金融都市香港は。経済発展とともに都市としての価値を向上させてきました。その象徴が不動産価格の上昇です。これまで家賃、教育費、生活費、医療費が高いと伝えてきましたが、実はその他全てにおける物価高の基礎が、不動産価値の上昇なのです。
景気が良くても、悪くても不動産価格が下がりにくい、更に長引く円安ドル高と経済発展が呼び込んだ不動産高騰、これが生活費高騰の理由です。
経済は発展して欲しいですが、生活苦にならないようにしていきたいですね。
3-3.値上げ率は今後も高止まり
香港の生活費については、今後も長期的に高止まりの状態が続くと見られています。
物価高の背景にある円安ドル高、不動産価値の高止まり、および中国を含めた経済発展は長期的であり、この2つが続く限り生活費の水準低下はない、といわれています。
香港に滞在する場合は、今後の物価上昇も想定したうえで生活費をシミュレーションする必要があるでしょう。
4.香港の生活費は日本の2倍以上!かしこく節約して海外生活をエンジョイしよう

日本でも香港でも都市部を中心に生活費の高騰が続いますが、東京都内と比較しても家賃だけで約1.5倍~2倍の開きがあります。
香港への移住やビジネス展開を検討する場合には、法規制や文化的な違いを理解し、対応していく必要があります。
110香港では、移住を踏まえたアドバイスから資産運用まで、幅広いサポートを提供しています。複雑な手続きやご不安がある方は、110香港の専門スタッフが一緒に最適な解決策を見つけますので、どうぞお気軽にご相談ください。
香港滞在をもっと充実させたい方へ
香港での暮らしや旅行をより楽しみたい方には、日本語で現地情報を発信している『香港グルメ図鑑』のサイトがおすすめです。
駐在員ならではの視点で厳選されたグルメ情報に加え、観光、ショッピング、越境移動など実用的な内容も豊富に掲載されています。初めての香港でも安心して使えるガイドとして、旅行前の情報収集や滞在中の参考にぜひご活用ください。
▶ 関連記事はこちら:【常にランキング1位】香港の物価が世界一高いのはなぜ?移住前に知るべき理由と生活費
海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ
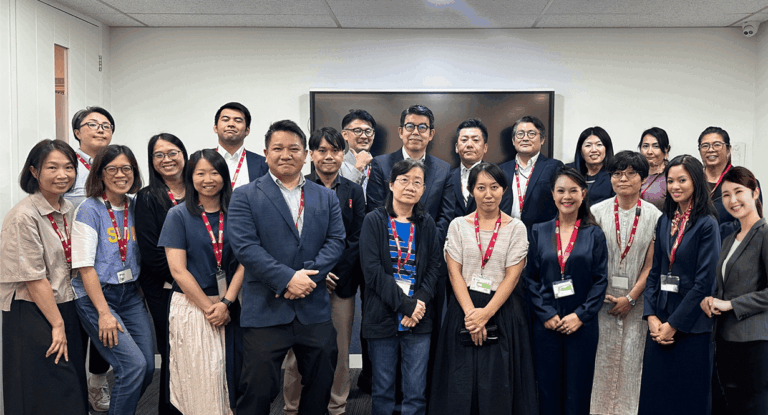
1998年に香港で金融サポートを開始したNNI香港の個人保険部門である「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規の保険BROKERとしての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、日本でのFP経験もあり日本事情にも精通する経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。
- 海外での資産運用が初めてで少し不安
- 今の資産運用状況についてのアドバイスが欲しい
- iDeCo/NISAや老後の年金について知りたい
といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
▼各種保険会社・商品の紹介はこちら
SUNLIFE HONGKONG(サンライフ香港)
├BRIGHT UL Wealth-Builder(ブライト UL ウェルスビルダー)
├Commitment(コミットメント)
├Generations II(ジェネレーションズ II)
├LIFE Brilliance(ライフ ブリリアンス)
├Stellar Multi-Currency Plan(ステラ マルチカレンシー プラン)
├SunGuardian(Care Version)(サンガーディアン(ケアバージョン))
├SunJoy / SunGift(サンジョイ / サンギフト)
├SunJoy Global(サンジョイ グローバル)
├SunProtect(サンプロテクト)
├SunWell(サンウェル)
├Venus II(ヴィーナス II)
├Victory(ビクトリー)
├Vision(ビジョン)
├Vital(バイタル)
CTF Life(旧FTライフ香港)
├“HealthCare 168 Plus” Critical Illness Protector(ヘルスケア168プラス クリティカルイルネスプロテクター)
├“On Your Mind” Insurance Plan(オンユアマインド保険プラン)
├Fortune Saver Insurance Plan II(フォーチュンセーバー保険プランII)
├Fortune Saver Insurance Plan Ⅲ(フォーチュンセーバー保険プランIII)
├MyWealth Savings Insurance Plan (Premier)(マイウェルス貯蓄型保険 プレミア)
├Regent Prime Insurance Plan II (Premier) / Regent Elite Insurance Plan II (Premier) / Regent Insurance Plan 2 (Premier Version)(リージェントプレミアシリーズ)
QDAP(税優遇年金制度)
├提供会社:AIA、FTLife、Sun Life ほか